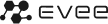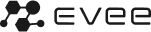前のページに戻る

もしもの時の備え
家庭用蓄電池とは? 仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
2025年7月22日 更新
エネルギー効率化のために注目されている蓄電池ですが、実際にどんなものなのか、どんなメリットがあるのかをご存じでしょうか。なんとなく、電気を蓄えることができるという認識はされているものの、仕組みまで知っている方は少ないかと思います。
もし、ご家庭に蓄電池を導入することに興味がある方は、そのメリットとデメリットもおさえておきましょう。
蓄電池とは?

初めに電池はいくつかに分類されますが、その中で一次電池と二次電池の2つの分類があります。
- 一次電池
一次電池とは、その電池の中に蓄えられている電気を一度完全に放電してしまったら捨てることになる、使い切りの電池のことです。 - 二次電池
二次電池とは、充電して繰り返し使える電池です。身近な二次電池には、パソコンやスマートフォンについている、リチウムイオン電池があげられます。蓄電池はこの二次電池にあたる電池であり、電気を蓄えることと放電することを繰り返し行うことができます。
蓄電池に蓄えられる2種類の電気

次に、蓄電池には2種類の電気を蓄えることができます。1つはみなさんのご家庭で契約している電力会社から送られてくる電気です。そしてもう1つは太陽光発電などで作った電気です。
電力会社からの電気は、基本的に使用量に対する料金単価が設定されており、料金プランによっては時間帯ごとにその料金単価が変動します。
例えば、昼間の電気料金単価が高く、夜間の電気料金単価が安いプランに加入していた場合、夜間に蓄電池へと電気を蓄えておき、その蓄えた電気を使うことにより電力会社からの電気は不要にすることができます。総合的に料金単価の安い時間帯の電気を使うことになるため、電気代がおトクになるということです。
いっぽう、太陽光発電で作った電気は、昼の太陽光発電の電気を蓄電池に蓄えておき、夜に使うことで電気代を抑えることもできます。
加えて、太陽光発電は再生可能エネルギー由来の電気として環境にやさしいというメリットもあります。また太陽光発電で作った電気を電力会社に売ることで収益を得ることも可能です。
さらに、太陽光発電設備と蓄電池をもっていれば、災害時など電力会社からの電気がストップしてしまった時には、ご自宅で発電と蓄電を行い電気が使えるようにしてくれる心強い味方となってくれます。
EV(電気自動車)も蓄電池の代わりになる

EVやPHEVは自動車ではありますが、大容量バッテリーの蓄電池としての見方もできます。家庭の電気をそのままEVへ充電でき、またEVから家庭への電力供給を可能にしてくれるV2H(Vehicle to Home)システムを使うことで、EVは蓄電池としての活躍もできます。
家庭用の蓄電池の容量はおおよそ10kWhほどですが、EVは軽自動車タイプでも20kWhあります。また、90kWhを超えるような大きな容量を持つ車種もあります。大きな容量を持ってはいるものの、実際にはそれだけの容量を使う長距離ドライブを頻繁にすることはなく、持て余し気味になっていることがあります。
そこで、V2Hシステムを利用し、EVに蓄えている電気を家庭に供給することで、大容量蓄電池として家庭用電源の頼りになる存在として活躍させることができます。
EVを蓄電池として活躍させることは、災害や停電時の備えにもなります。
家庭用蓄電池の仕組みを簡単に解説
蓄電池が家庭の電気をおトクに、また安定して使えるようにしてくれるものであることがわかりましたが、実際にどんな仕組みになっているのかを見てみましょう。
まず、蓄電池はそれ単独では家庭の電気を使用できません。パワーコンディショナーと呼ばれる機器を必要とします。このパワーコンディショナーは電気の交流と直流を変換してくれる機器になっています。
蓄電池の中にある電気は直流になっているのですが、家庭の電気は交流です。そのままでは使うことができないため、パワーコンディショナーが直流電気を交流電気に変えてくれるのです。変換時には若干の電気ロスが生じてしまうことは覚えておきましょう。
パワーコンディショナーが変換してくれた電気を蓄電池に溜めていくことになりますが、蓄電池の中では化学反応が起こっています。具体的には電池のプラス極とマイナス極2つの電極の間をイオンが移動することで化学エネルギーとして電気を保存できるのです。
また放電をする、つまり蓄電池に蓄えていた電気を家庭に供給する場合には、この反応が逆方向に進行することになります。蓄電池内の化学エネルギーが電気に変換されて外へと出ていくのです。
多くの蓄電池にはリチウムイオンが採用されています。リチウムイオンは小さくてパワフル、また長持ちすることから先ほどのEVやPHEVの他、スマートフォンのバッテリーなど様々なところに利用されています。
もちろん、リチウムイオン以外の蓄電池もありますし、電池の種類によっては電気を蓄えたり放出する仕組みも異なりますので、あくまで一般的な蓄電池の仕組みとして覚えていただけたらと思います。
家庭用蓄電池のメリット
家庭用蓄電池がどんなもので、その仕組みについても大まかに理解できたと思います。次は、この蓄電池のメリットをあげていきます。
災害や停電のときにも家庭で電気が使える
家庭に蓄電池を持つということは、何よりも電気が止まってしまった際の非常電源を持てるというメリットがあります。近年は地震や台風などの災害が多く、一時的でも停電が起きてしまうことがあります。そのような時、蓄電池に電気が蓄えられていれば、家庭用蓄電池は非常電源として活躍してくれます。
スマートフォンの充電、照明やエアコンの使用、冷蔵庫を使うなど、万が一の備えになるということは、蓄電池の最大のメリットと言えます。環境省では1世帯が1年間に消費したエネルギーは、全国平均で電気が4,175kWhとされていますので、1日換算ですとおおよそ11kWhとなります。
参考:家庭のエネルギー事情を知る 「令和3年度家庭部門のCO2排出実態統計調査資料編(確報値)」 環境省
そのため、すべての電気使用量を賄うことは難しいですが、最低限の電気を供給することは可能です。
また、もしもEVを保有しさらにV2Hシステムを用いてEVに蓄えている電気を家庭に供給できれば、40kWhのバッテリー容量のEVで3日間はいつもどおりの電気を使う生活ができる計算になります。
電気代を安くできる
燃料費高騰の影響を受けて、電気代も値上げされている、といったニュースを聞いたことのある方も多いでしょう。電気代の高騰が騒がれる中で、家庭用の蓄電池は節約の助けにもなってくれます。
電気料金単価が安い時間帯に蓄電池に電気を蓄えておき、単価が高い時間帯に放電して家庭の電気を使えば、結果的に料金単価の安い時間帯にだけ電気を使っていることとなり、電気代の節約ができます。
先にお伝えしたような太陽光発電設備と一緒に使用することで、さらに電気代をおトクにすることもできるでしょう。
家庭用蓄電池のデメリット

確かに蓄電池は、家庭の電気の安定に貢献してくれますが、デメリットもありますので触れておきます。
導入費用
まずは初期費用がかかるという点です。蓄電池本体の購入費用もかかりますが、設置工事や電気工事にかかる費用も考慮しなくてはいけません。
パワーコンディショナーなどの機器にも費用が掛かります。こうしてかかった費用は、蓄電池をうまく活用することで節約できる電気代で少しづつ回収することになりますが、導入する際にまとまってお金がかかることは大きな負担になります。
蓄電池をうまく活用できない
蓄電池のメリットには、電気料金単価が安い時間に電気を蓄え、高い時間に使うという点を挙げましたが、すべてのご家庭でそのような活用ができるわけではありません。
ご契約されている電力プランによっては、料金単価が時間で変動しない場合もありますし、容量が足りずにあまり蓄電池からの電力供給ができず、結局電力会社からの電気を使うことになるかもしれません。
家庭用蓄電池の導入には、今現在の電気料金プランの再確認や実際にご家庭で必要な電力量を把握したうえで、十分な容量のある蓄電池を購入するなど、しっかりとした検討が必要です。結論として蓄電池が向いていないという場合もありますので、万能な設備とは言えないのです。
蓄電池の置き場所を考える
蓄電池を設置する場所というのも考えなくてはいけません。小型になってきているといっても一定のスペースを確保しなくてはいけませんし、直射日光を避け高温多湿な場所には置かないなど、どこにでも置けるわけではないのです。
また、蓄電池には室内用と室外用があり、動作音によってはとても気になり日常生活に支障をきたす場合もあります。いざ蓄電池を活用し、電気料金単価の安い深夜に蓄電を始めたら、うるさくて眠れないなんてことになっては本末転倒です。
蓄電池がただの置物になってしまうということのないように、置き場所には注意しましょう。
寿命がある
蓄電池は蓄電と放電を繰り返していくことで徐々に劣化していきます。バッテリーが経年劣化して起きる現象なので仕方のないことですが、半永久的な非常電源というわけにはいかないのです。
蓄電池には、このバッテリー寿命がありますので、購入する際に有効期間を調べて買い替えのタイミングと費用を考慮しなくてはいけません。廃棄処分においては、通常のごみとしては捨てられない有害物質を含む場合があるので専門業者へ依頼したり自治体指定の集積場へ持ち込む必要がある場合も考えられます。
家庭用蓄電池は、電気を溜めておくことで、停電時に備えたり、電気代を節約したりできる便利な装置です。また、太陽光発電と組み合わせることで、さらに効果的に活用できます。自分のライフスタイルに合った蓄電池を選び、安心でエコな生活を送りましょう。