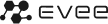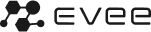前のページに戻る
.jpg&w=750&q=75&dpl=dpl_GGwXWYt1MJWeEfrekok2GDp6n1p2)
再エネ・発電の仕組み
電力需給ひっ迫とは? EVとともに暮らす時代に知っておきたいこと
2025年7月29日 更新
皆さんは「電力需給ひっ迫」という言葉をニュースなどで耳にしたことはあるでしょうか?
普段あたりまえのように使っている電気ですが、実は限りある資源です。電力の供給量(発電できる電気の量)が、需要(使いたい電気の量)に対して足りなくなる可能性がある、もしくはすでに足りていない状態のことを「電力需給ひっ迫」あるいは「電力不足」と呼びます。
実際に、2022年3月22日には、東京・東北エリアでこの「電力需給ひっ迫」が現実となり、政府が「需給ひっ迫警報」を初めて発令。官邸や経済産業省などから、節電への協力要請が出されたのをご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。
このときは1日でひっ迫状態が解消され、大規模停電には至りませんでしたが、当時の状況は非常に深刻で、まさに社会全体が電気のありがたさを再認識した瞬間でもありました。
では、なぜ電力が足りなくなるような事態が起きてしまうのでしょうか? そして、電気をより多く使うようになるこれからの時代――たとえば電気自動車(EV)が普及していく中で、私たちはこの問題にどう向き合っていくべきなのでしょうか。
このコラムでは、電力需給ひっ迫が起きる背景やその原因をわかりやすく解説するとともに、EVユーザーをはじめとする私たち一人ひとりができる節電・対策のヒントをご紹介していきます。
電力需給ひっ迫とは?
.jpg)
電力需給ひっ迫とは、電気の需要が供給量の上限に近づく状態を指します。このような状態になると、電力が安定して供給されなくなり、大規模な停電(ブラックアウト)につながるリスクが高まります。
電力需給ひっ迫の目安とは?
では、どれくらい発電量と電力の需要が近づくと「電力ひっ迫」と呼ばれるのでしょうか?経済産業省によると、安定した電力供給のためには、全国すべてのエリアで最低限「予備率3%」が必要とされています。予備率とは、需要に対してどれだけ余裕のある発電能力があるかを示す割合のことです。
この予備率が3%を下回ると、電力の安定供給が難しくなり、警報が発令されることもあります。
さらに、天候の急変や発電設備のトラブルに備えるため、実際には8~10%程度の予備率を確保することが望ましいとされています。これにより、万が一の事態にも対応できる体制が整うわけです。
参考:経済産業省 資源エネルギー庁 電力需給対策について 2023年6月27日
なぜ電力ひっ迫が起きるのか?
.jpg)
原因のひとつは電気の「使われ方」と「作られ方」のバランスが崩れていることにあります。
需要(使う側)の問題
・家庭で使う家電製品の増加 ・猛暑・厳冬など、気候変動にともなうエアコンや暖房の利用拡大 ・近年では、EV(電気自動車)など電力を使う新しいインフラの普及も加わりつつあります
供給(つくる側)の問題
・火力発電所の老朽化やメンテナンスによる停止 ・再生可能エネルギーの出力が天候に左右されやすい ・世界的な燃料不足や価格高騰
電気は基本的に「その場で発電し、その場で使う」もの。水やガスのように大量にためておくことが難しいため、発電と消費のバランスを常にとり続ける必要があります。
これからの時代に向けて:EVと電力の付き合い方
電気を「使う」側として、EVオーナーの皆さんにもできることがあります。
たとえば、ピーク時間(特に夏の夕方など)を避けて充電することで、電力使用の分散につながります。
今後、EVのバッテリーを一時的に家庭や地域の電力源として活用する「V2H(Vehicle to Home)」や「VPP(仮想発電所)」といった取り組みも進んでいくと考えられます。
ディマンドリスポンス(DR)とEVオーナーができること
.jpg)
ディマンドリスポンス(DR)は、消費者が電気の使い方を賢く調整して、電力の需要と供給のバランスを保つ仕組みです。
一般的には電力会社が需要に合わせて発電量を調整しますが、DRでは消費者側が電気の使用量を調整することで、電力の安定供給を支えます。
特にEV(電気自動車)オーナーの方は、DRの中でも「V2G(Vehicle to Grid)」という仕組みに参加できます。V2Gは、EVのバッテリーに蓄えた電気を、必要な時に家庭や電力網に戻すことができる技術です。
これにより、電力のピーク時にEVから電気を放電して需要を減らす手助けができるため、電力ひっ迫の解消に大きく貢献します。
また、DRの「インセンティブ型」では、電力会社からの要請に応じて電気使用を抑えたり、V2Gを活用したりすることで、電気代の節約に加え報酬を受け取れるメリットもあります。
EVオーナーの皆さんがこうした仕組みに参加することは、安定した電力供給を支えるだけでなく、経済的なメリットも期待できる大切な役割です。
参考:ディマンド・リスポンスってなに? 経済産業省 資源エネルギー庁
電力を「かしこく使う」意識が、未来を守る第一歩
電力需給のひっ迫は、誰にとっても無関係な話ではありません。電気に依存する私たちの生活だからこそ、一人ひとりができる工夫や意識の積み重ねが、安定した電力供給を支える大きな力になります。
EVがある生活をもっと快適に、そして安心して続けていくためにも、「電気をどう使うか」を一緒に考えていきましょう。