前のページに戻る

再エネ・発電の仕組み
再生可能エネルギーとは?初心者にもわかる基本とEVとの深い関係
2025年7月31日 更新
再生可能エネルギーという言葉は、いまや多くの人に知られるようになりました。しかし、太陽光や風力といった名前は聞いたことがあっても、それぞれがどんな仕組みで発電され、どんな特徴を持っているのかまで理解している人は、まだ多くないかもしれません。
そして近年では、再生可能エネルギーと電気自動車(EV)の関係にも注目が集まっています。再エネ由来の電力でEVを走らせることができれば、走行時だけでなく、充電時にも環境負荷を抑えられるため、よりサステナブルな移動手段としての価値が高まるからです。
今回は、そんな再生可能エネルギーの種類やメリット・デメリットについて、EVのある未来を想像しながら、あらためてわかりやすくご紹介していきます。
再生可能エネルギーとは?
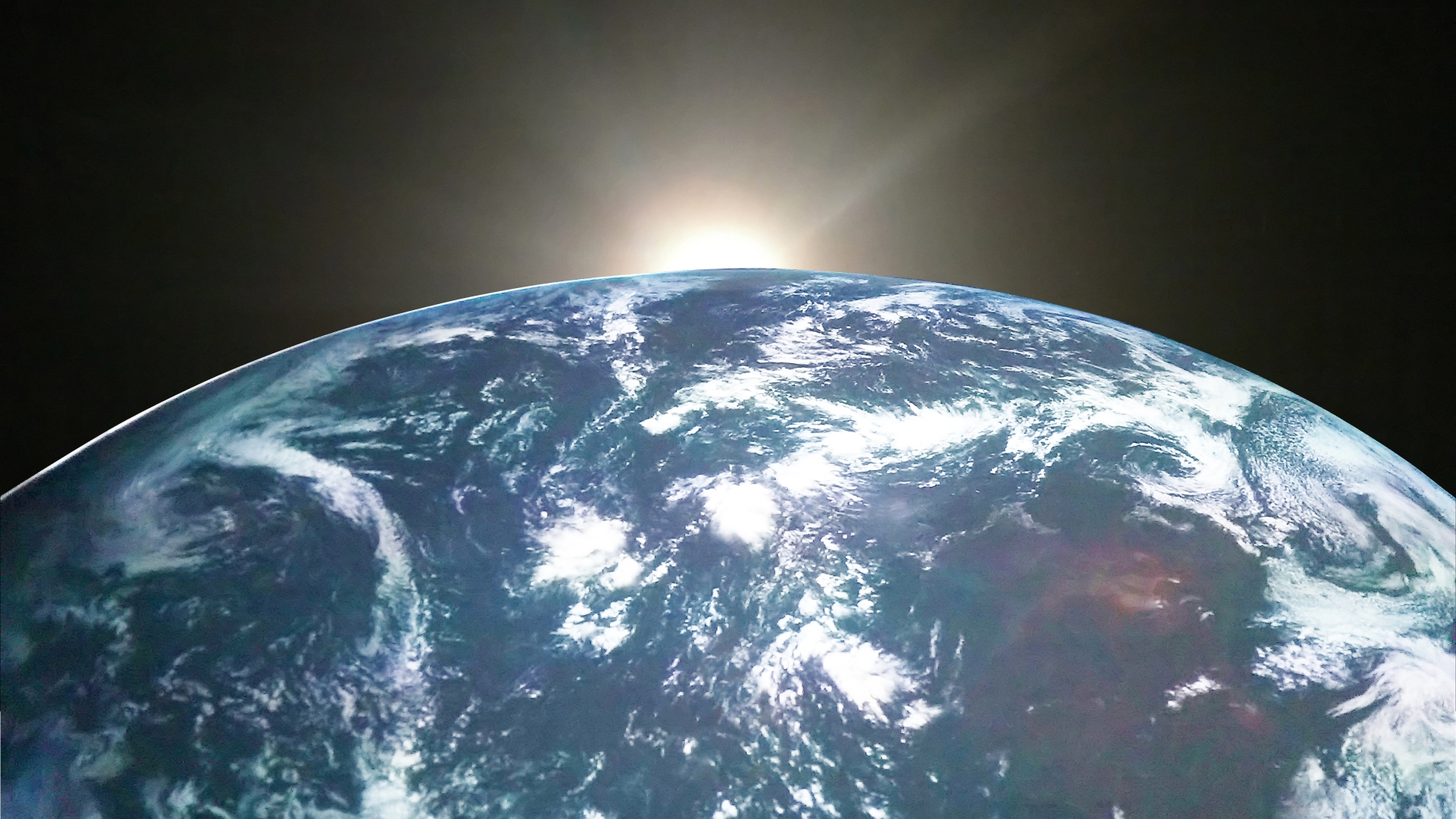
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱など、自然界に常に存在していて、ほぼ無限に利用できるエネルギー源のことを指します。
石油や石炭、天然ガスといった有限な化石燃料とは対照的に、枯渇の心配がなく、繰り返し利用できるのが大きな特徴です。
これらの再生可能エネルギーは、環境への負荷が少なく、持続可能な社会を目指すうえで欠かせないエネルギーとして、世界中で注目されています。とくにEVとの相性が良く、再エネ由来の電力でEVを充電することで、走行時のゼロエミッションに加え、ライフサイクル全体でのCO₂削減にも貢献できます。
再生可能エネルギーの主な特徴は、次の3つです。
- 枯渇しない:太陽や風、地熱など自然の力を使うため、尽きることがありません
- 普遍的に存在する:多くの地域で利用可能で、エネルギーの地域自立にも貢献します
- CO₂を排出しない(または増加させない):燃焼を伴わない発電が多く、気候変動対策としても有効です
クリーンな電力源とは?再生可能エネルギーの種類と特性を整理
太陽光発電:もっとも身近な再エネ、EVとの相性も良好

太陽光発電は、太陽の光を太陽電池モジュールに当てて、光エネルギーを電気に変える発電方法です。住宅の屋根や空き地など、日当たりのよい場所にパネルを設置することで、自家消費用の電力をまかなうことができます。
化石燃料を使わず、太陽が出ているあいだは安定して発電できるため、非常にクリーンで持続可能なエネルギー源として注目されています。特に、EV(電気自動車)と組み合わせることで、自宅で発電した電力をEVの充電に活用するなど、環境にやさしいエネルギー循環が可能になります。
一方で、天候に左右されやすく、夜間や曇天時には発電量が大きく低下します。
また、設備導入時のコストが高めであることも普及のハードルとなっていますが、近年は補助制度や電力売買の仕組みも整いつつあり、導入のハードルは少しずつ下がってきています。
風力発電:夜間も発電可能な再エネ、EVの安定供給を支える存在に

風力発電は、風の力で風車(タービン)を回し、その回転によって発生するエネルギーを電気に変換する発電方法です。風という自然の力を利用するため、温室効果ガスを排出せず、地球環境にやさしいのが大きな特徴です。
日本では、風速や風向きの条件が良い北海道・東北・九州地方を中心に設置が進んでいます。風力発電には陸上に設置する「陸上風力」と、海上に設置する「洋上風力(着床式・浮体式)」があり、特に今後は広大な海を活用した洋上風力の拡大が期待されています。
参考:一般社団法人 日本風力発電協会 第2回洋上風力官民協議会が開催され、洋上風力産業ビジョン(第1次)が発表されました。2020年12月15日
風力発電のメリットは、風さえあれば昼夜を問わず発電できることです。
これにより、太陽光発電が苦手とする夜間の電力供給を補える可能性があります。EVと組み合わせれば、自然エネルギーによる持続的な充電環境の構築にもつながります。
一方で、発電設備の建設や調整にかかるコストが高く、日本の地形的な制約もあって、導入はまだ限定的です。それでも再エネの中では発電効率が高く、今後の技術革新や制度整備によって普及が進むことが期待されています。
水力発電:日本に根づいた再エネ、安定供給でEVインフラの一翼も

水力発電は、高い場所から低い場所へ水を流し、その水の勢いで水車を回して電気を生み出す発電方式です。自然の重力と水の力を活用するため、環境への負荷が少ないのが特徴です。
日本は山地が多く、河川も豊富なため、水力発電は早くから全国各地で導入されてきました。発電の方式には「流れ込み式(水路式)」「調整池式」「貯水池式」「揚水式」などがあり、いずれも大規模なインフラ整備を必要とします。
水力発電の大きなメリットは、気候や天候に大きく左右されず、安定的に電力を供給できる点です。こうしたベース電源的な役割は、今後EVが普及していく中で、充電インフラの安定化にも寄与する可能性があります。
また、日本国内には長年の運用で蓄積された技術やノウハウがあり、既存の施設を活用しやすい点も強みです。
一方で、ダムや取水施設の建設には高い初期投資が必要で、環境影響評価や河川状況の長期調査などに時間がかかる点が課題です。それでも、既存インフラを活かした再整備や小水力発電の導入によって、今後の再エネ電源としてさらに注目される存在です。
バイオマス発電:廃棄物をエネルギーに変える、循環型社会の電源

バイオマスとは、家畜の排せつ物、農業の副産物、食品廃棄物、木材など、動植物由来の再生可能な資源の総称です。バイオマス発電では、これらを燃料として燃やし、その熱エネルギーでタービンを回して電気を生み出します。
バイオマスが燃焼する際に排出されるCO₂は、原料となる植物が生育過程で吸収したCO₂とほぼ同量とされており、大気中のCO₂を実質的に増やさない「カーボンニュートラル」な発電方法と位置づけられています。
特に注目されるのは、廃棄物の有効活用によってゴミを減らしながら電力を得られる点。たとえば食品ロスや家畜排せつ物といった、これまで廃棄されていた資源を活かすことで、循環型社会の実現に貢献します。
また、安定的に燃料を確保できれば、天候に左右されにくい電力供給が可能なため、今後EV充電ステーションの地域分散においても補完的な電源として期待されます。
一方で、バイオマス燃料は広範囲に点在しているため、回収・運搬・保管にコストがかかり、特に人口の少ない地域では効率的な発電体制の構築が難しいという課題もあります。
それでも、未利用資源を地域で循環させる小規模発電の仕組みなど、新たな取り組みにより、持続可能なエネルギー源として注目が高まっています。
地熱発電:日本の地下資源を活かす、安定供給型のクリーンエネルギー

地熱発電は、地中深くにあるマグマの熱を活用して、地下から取り出した高温の熱水や蒸気でタービンを回し、電気をつくる発電方式です。
この地熱エネルギーは、化石燃料のように枯渇する心配がなく、長期間にわたり安定的に利用できる再生可能なエネルギー源です。特に火山帯に位置する日本では、地熱資源が豊富であり、地理的な優位性を活かした電源として注目されています。
地熱発電のメリットは、燃料を必要とせず、二酸化炭素などの温室効果ガスをほとんど排出しない点です。また、天候や昼夜の影響を受けず、ベースロード電源(常に安定供給できる電源)として機能するため、風力や太陽光と組み合わせた電力安定化にも寄与します。
一方で、地熱発電の導入には高い初期投資と、地質調査・掘削・環境アセスメントなどの準備に時間がかかるという課題があります。また、温泉地との資源利用の調整が必要な場合もあり、地域との合意形成が不可欠です。
それでも、発電所が稼働すれば長期的に安価で安定した電力が得られるため、今後のEV充電インフラや分散型電源としての可能性も広がっています。
再生可能エネルギーのメリット
環境にやさしい
再生可能エネルギーの一番のメリットは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスをほとんど出さない、または排出量を増やさないことです。
温室効果ガスは、地球の平均気温を上昇させ、気候変動や自然災害のリスクを高める原因となっています。こうした問題に対応するため、世界各国は「パリ協定」に基づき、温室効果ガスの削減目標を掲げています。
その目標を達成するためには、石炭や石油などの化石燃料に頼らず、太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーへ切り替えていくことが重要です。持続可能で、次の世代にも安心して引き継げるエネルギーとして、今まさに注目されています。
再生可能エネルギーでエネルギー自給率を高める
日本はエネルギー資源に乏しく、2020年度のエネルギー自給率はわずか11.3%にとどまっています。
参考:経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」
多くのエネルギー資源を海外からの輸入に頼っているため、国際的な情勢の変化や燃料価格の高騰などによって、エネルギーの安定供給が脅かされるリスクがあります。
その一方で、太陽や風、水、地熱といった再生可能エネルギーは、国内で利用できる自然の力を活用する方法です。これらを積極的に導入することで、日本でもエネルギーの自給率を高め、安定したエネルギー供給体制を築くことができます。
資源に限りがある日本にとって、再生可能エネルギーは「持続可能な未来」をつくるための鍵となる存在です。
再生可能エネルギーのデメリット
発電の不安定さ
再生可能エネルギーは、天候や自然環境の影響を強く受けるため、発電量が一定しないという課題があります。
たとえば、太陽光発電や風力発電は、天候だけでなく季節や時間帯によっても発電量が変動します。冬場や夜間は太陽光が不足し、風も弱まることがあり、その結果、発電量が減ることがあります。
こうした変動を補うために、蓄電技術の重要性が高まっています。蓄電池を活用することで、発電量が多い時に余った電力を蓄え、需要が高まった際に供給できるようにすることが可能です。
導入にかかるコスト
太陽光パネルや風力タービン、水力発電設備などの再生可能エネルギー施設の設置には、初期投資が高額になることが少なくありません。
さらに、設備の保守や運用にも継続的なコストがかかり、定期的な点検やメンテナンスも必要です。
しかし、近年は製造技術の進歩により太陽光パネルや風力タービンのコストが下がってきており、政府の助成金や補助金も充実しているため、導入コストの負担は徐々に軽減されています。
必要なスペースの広さ
再生可能エネルギーの種類によって必要な敷地面積は異なります。
太陽光発電は広い面積を必要とし、風力発電は風通しの良い広域な場所が適しています。水力発電には水のある地域が欠かせず、バイオマス発電は資源の保管や処理に一定のスペースが求められます。
地熱発電は地熱帯に限定されるため、他の方法に比べて敷地の条件は緩やかです。
このように、一定の土地やスペースを確保しなければならない点も、再生可能エネルギーの課題のひとつです。
持続可能な未来への一歩
.jpg)
ここまで再生可能エネルギーについてご説明してきました。
大規模な発電所による再生可能エネルギーの活用が進む一方で、ご自宅の屋根に太陽光パネルを設置して自家発電を行うことも可能です。さらに、再生可能エネルギーを重視した電力会社のプランも増えており、環境に配慮した選択肢が広がっています。
また、電気自動車(EV)の普及は再生可能エネルギーとの相性が非常に良い点も見逃せません。EVの充電に再生可能エネルギーを利用すれば、走行中のCO2排出を抑えられるだけでなく、家庭の余剰電力を活用したエネルギーマネジメントも可能になります。
例えば、太陽光発電で余った電力をEVに充電し、必要に応じて車のバッテリーから家庭へ電力を戻すことも技術的に進んでいます。
このように、再生可能エネルギーの理解と活用は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であるとともに、EVとの連携によってより効果的に地球環境への負荷軽減に貢献できます。
私たち一人ひとりがこの流れに参加することで、エネルギーの枯渇や環境問題の解決に向けた取り組みを加速させていけるでしょう。
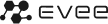
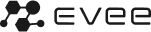
.jpg&w=750&q=75&dpl=dpl_GGwXWYt1MJWeEfrekok2GDp6n1p2)
